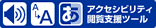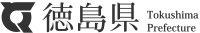敷地遺跡
しきじいせき
所在地
徳島市国府町敷地
古墳時代の遺跡
遺跡概要
敷地遺跡は鮎喰川左岸の沖積地上、標高約5mの微高地上に立地しており、弥生時代後期~中世にかけての複合遺跡である。1998年(平成10年)から道路建設に伴う発掘調査が継続的に行われている。
敷地遺跡(古墳時代)
キーワード
古墳時代後期の集落跡
概要
古墳時代の遺構は竪穴住居跡、掘立柱建物、土壙墓、溝などが検出されている。竪穴住居跡は古墳時代中期と古墳時代後期の2時期のものが存在している。古墳時代中期の竪穴住居跡は東壁に竈(かまど)を設けており、古墳時代後期の竪穴住居跡では北壁に竈(かまど)に設けているという特徴がみられる。
敷地遺跡の集落は、県下最大規模の古墳群である気延山古墳群の最も近くに位置している。これらの古墳群の造営に関わっていた人々の集落の可能性が高い。
問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
徳島県埋蔵文化財センター年報 vol.10~15 「敷地遺跡」1999年~2004年
敷地遺跡(古代)
キーワード
国司の館跡
概要
古代の遺構は掘立柱建物跡、土壙墓、水田跡などが検出されている。注目されるのは整然と配置された掘立柱建物群である。「L」字や「コ」字形に規則正しく配置されており、建物に隣接して大きな井戸が築かれていたことから役人の住まいであろうと考えられる。
また役人など身分の高い人が執り行ったとみられる祭祀行為に伴う遺物(斎串、刺串、刀形木製品、陽物、土馬など)や、郡名を記載した木簡が出土しているため、国司クラスの人物の館であった可能性が高いとみられる。
問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
徳島県埋蔵文化財センター年報 vol.11 「敷地遺跡」 2000年
敷地遺跡(中世)
キーワード
中世の杮(こけら)経
概要
敷地遺跡の中央部を流れる西大堀川から2289点の杮(こけら)経が出土した。これらは束状にされて川に流されたと考えられる。このうちの765点で文字が読み取れた。書かれていたお経の大部分が「般若理趣経」であった。重複する部分があって、少なくとも4組の杮(こけら)経が束ねられていたと考えられる。出土した土器からは室町時代のものと考えられている。周辺からは形の整った土器が大量に出土していることから、この川岸で何らかの儀式が行われていたと考えられる。


問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
徳島県埋蔵文化財センター年報Vol.1 2002年
『木簡研究第26号』木簡学会 2004年