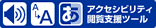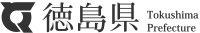貞光前田遺跡
さだみつまえだいせき
所在地
徳島県美馬市つるぎ町貞光東浦及び前田
遺跡の概要
貞光前田遺跡は吉野川の支流、標高約60mの貞光川左岸の河岸段丘上に形成された遺跡である。吉野川との合流地点から約1.5?上流の高台に位置し、1994年(平成6年)~1995年(平成7年)にかけての学校建設に伴う発掘調査で、縄文・弥生・鎌倉・室町の各時代の遺構や遺物が発見された。

貞光前田遺跡(縄文時代)
キーワード
縄文時代 中・後期の集落
概要
縄文時代の遺構、遺物は、後期の竪穴住居跡3棟のほか、中期の船元・里木式土器、後期前半の中津式・福田K2式・松ノ木式・津雲式など摩消縄文や縁帯文土器と呼ばれる、近畿から瀬戸内・四国にかけて広く分布する、土器や石器が多く出土した。検出された竪穴住居は、後世の削平を多く受けているため正確な形は不明だが、隅丸方形の平面形を持つ後期の縁帯文土器の時期の遺構であったと考えられる。石器はサヌカイト製の打製石鏃や片岩製のスクレイパー・敲石・磨石・石錘などが出土した。縄文時代の竪穴住居が土器や石器を伴って複数出土しており、当時の生活を復元する上で重要な遺跡である。

問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
徳島県埋蔵文化財センター調査報告第35集「貞光前田遺跡」2001年
貞光前田遺跡(弥生時代)
キーワード
弥生時代後期から古墳時代初頭、土器の廃棄土坑、水銀朱の精製遺跡
概要
弥生時代では、竪穴住居跡14棟と掘立柱建物跡6棟が確認された。そのうち1棟の竪穴住居跡では大量の土器が出土したことから、住居を廃絶した後に土器をすてる場所にされていたと考えられる。
また、水銀朱が付着した石器が出土していることから、遺跡内において朱の精製が行われていた可能性が指摘されている。
問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
徳島県埋蔵文化財センター調査報告第35集「貞光前田遺跡」2001年