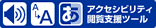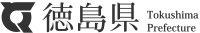名東遺跡
みょうどういせき
所在地
徳島県徳島市名東町
概要
鮎喰川右岸の沖積地上、標高約10mの微高地上に立地しており、縄文時代~中世にかけての複合遺跡である。
1970年代以降宅地開発などに伴って、数十回にも及ぶ発掘調査が行われている。|
名東遺跡(縄文時代)
キーワード
縄文時代晩期の土器が出土
概要
1987年(昭和62)年徳島市教育委員会によって、天理教国名大教会の建設地点の調査が行われている。調査区からは溝状の窪地が検出されており、縄文時代晩期終末の突帯文土器がまとまって出土している。その他に石鏃・石棒などの石器類も出土しており、徳島の縄文時代の終末期を考える上で重要な資料である。
問い合わせ先
徳島市教育委員会
参考文献
徳島市教育委員会「名東遺跡発掘調査概要」1990年
名東遺跡(弥生時代)
キーワード
水銀朱の精製と銅鐸が埋納された弥生時代の集落
概要
1987年(昭和62年)に徳島市教育委員会によって実施された天理教国名大教会地点では、扁平鈕六区袈裟襷文銅鐸が方形周溝墓群の一角に埋納されていた。銅鐸が埋納された時期は、周辺の遺構の年代などから弥生時代中期末(約2,000年前)頃と考えられる。また1992年(平成4年)に発掘調査が実施された国土交通省宿舎地点では、中期末頃の水銀朱の精製工房とみられる竪穴住居跡が発見されている。


問い合わせ先
徳島県立埋蔵文化財総合センター
参考文献
名東遺跡発掘調査委員会『名東遺跡発掘調査概要 』1990年
徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第14集「名東遺跡」1995年