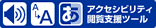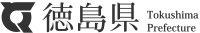2017アワコウコ楽連続公開講座「四国の埴輪」「人物埴輪の起源と葬送儀礼」を開催しました
現在,開催している発掘へんろ展「四国のハニワ」にあわせて,アワコウコ楽連続公開講座を開催しました。
「四国の埴輪」は2018年2月18日(日)に,「人物埴輪の起源と葬送儀礼」は3月4日(日)に実施し、両日あわせて131名の方に御出席いただきました。
「四国の埴輪」では,埴輪にみられる特色など四国各県の調査報告を行い,「人物埴輪の起源と葬送儀礼」では大正大学 塚田良道さんに,埴輪の表現方法から男女や身分差の見分け方,人物埴輪の起源について,御講演いただきました。
また出土数が少ないながらも「琴をひく」人物埴輪の存在から,箏演奏家3名の御協力を得て箏の演奏を行いました。

「香川県域における古墳時代前期の埴輪-近年の調査成果を中心に」と題して、お話をする高松市創造都市推進局文化財課の高上さん。
近年の発掘調査成果から,埴輪からみえてくる古墳時代前期の香川県の地域社会についてお話しいただきました。

「渦巻き文様を描く盾形埴輪」と題して、鳴門市大代古墳から出土した盾形埴輪を中心にお話しする公益財団法人 徳島県埋蔵文化財センターの藤川さん。

「伊予の形象埴輪~「鶏」と「馬」から何を読み取るか~」と題して,お話しする松山市教育委員会文化財課の山内さん。
愛媛県で多く見られる鶏形と馬形の形象埴輪を中心に、形象埴輪を見るときの山内さんの注目ポイントをご紹介いただきました。

「須恵質の埴輪をもつ伏原大塚古墳」と題して,公益財団法人 高知県文化財団埋蔵文化財センター 久家さんに高知県の古墳時代の状況をお話いただきました。
高知県では,埴輪が出土した古墳はこの伏原大塚古墳のみで,作り方も独特です。

3月4日(日)「人物埴輪の起源と葬送儀礼」の様子。人物埴輪のうち,男性を表した埴輪の見分け方・身分差について説明する塚田さん。

また聴講の女性に御協力いただき,女子埴輪の袈裟状衣について,持参した絹布で説明していただきました。
着用の実演により,後ろの画面(右側)にある,大阪府今城塚古墳から出土した女子埴輪の袋状に膨らんでいる箇所の理由がよくわかりました。

講演を2部に分け,その合間に箏の演奏を2回行いました。1回目の箏の演奏は,平岡さんによる「古代からのメッセージ」。
古墳時代の楽譜は残っていませんが,古代では「曲を弾く」というのではなく「琴をかきならす」そうです。
琴と現代の箏の違いの説明を受けた後,平岡さんの思う古代の琴の音が,参加者の方を古代に誘います。

2回目の講演の後は,3人で演奏。それぞれ曲に応じて箏を変え,調弦し,近世箏曲の祖である八橋検校作といわれる「箏独奏 六段の調」からはじまり,
「さくら三重奏」「ハナミズキ」と5曲演奏いただきました。調べから,過去から現代へ帰ってきたような感じでした。

大正大学 塚田さんと箏演奏家の平岡さん・山本さん・坂東さん。徳島県上板町と愛媛県松山市から出土した,女性の人物埴輪と一緒に撮影しました。
箏演奏家の方が着ている衣装は、古代をイメージして自分達で製作されています。