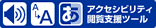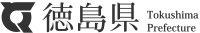2017年3月バスツアー「吉野川中流域の遺跡めぐり」
3月5日(日)、心配していた天気も風もなく、良いお天気となりました!ツアーにご参加いただいた皆々さまの日頃の行いが良かったようです。
朝9時前にバスに乗り込み、最初のお城「脇城」へ向けて出発です!
最初の目的地「脇城」は、阿波の西部において戦略上要衝の城であり、県内最大規模の山城を持ちます。天文2(1533)年に三好長慶が改修し、家臣の三河守兼則が守っていましたが、弘治2(1556)年に武田信玄の異母弟である武田信顕が入城します。天正7(1579)年に長宗我部氏が美馬郡を制圧したあと、長宗我部氏と三好方は脇城をめぐって2度争戦い、羽柴秀吉による四国攻めまで脇城は長宗我部氏の支城となります。
現在でも見ることができる山城の大規模な堀切や竪堀、石垣などは、阿波九城の頃の改修によるものとされ、外郭線もこの時期のものと考えられます。武田氏の頃の脇城は、県内の中世城郭の規模から考えると、主郭1程度の大きさだったと考えられます。
今回のツアーは目的地近くまで大型バスで乗り入れることは出来ないので、徒歩がメインのぶらりツアーです。脇城にあがる手前でバスを降り、まず脇城周辺の説明を受けます。


主郭にいたるまでの坂がきつかったですが、説明を聞きながら、脇城の主郭3→主郭2→主郭1に向かって進んでいきます。


主郭1へ向かいます。

ここは、主郭1と主郭2の間にある大規模な堀切です。2014年に訪れた時と比較して竹が生育範囲を拡大していました。
主郭1に到着!
うだつの町並みの中にある美馬市観光文化資料館の一室をお借りして、昼食タイムとなります。うだつの町並み目指して、山城をあとにします。

脇城は標高100mの河岸段丘城に位置する山城と、山城南麓の平地にあったとされる居館跡から成り立ちます。居館跡は、旧の字
「大屋敷」にあったと考えられていますが、現在は宅地が密集しており、後年の開発により当時の面影を残すものはほとんどあり
ません。しかし、濠跡とされる水路や土塁の残欠が現在も確認でき、これらと江戸時代の絵図を照らしあわせて考えると、北に山城、
その他の三方を推定幅6〜8mの濠、幅10m余りの土塁に囲まれた東西220m、南北200mのほぼ正方形の区画が大屋敷、稲田氏の
居館跡と考えられています。
展望の良い場所で、居館跡があったとされる平地を眺め、当時に思いを馳せます。
麓には徳島藩筆頭家老稲田家の菩提寺である貞真寺があります。このお寺には、美馬市指定文化財の「稲田墓所」や「貞真寺山門」があります。

お昼ご飯で一息ついて、2つめの目的地「重清城」へ。重清城も大型バスが近くまで行けないので、県道12号線沿いで降車。重清城までは、重清西小学校南側にある八幡1・2号墳や八幡神社、大国魂古墳、倭大国魂神社に立ち寄りながら向かいます。

八幡古墳群・大国魂古墳は、ともに「段の塚穴型石室」と呼ばれる横穴式石室をもちます。美馬町字坊僧にある国指定史跡「段の塚穴」の石室と形態や築造方法に共通点があり、特に大国魂古墳は段の塚穴型石室を持つ古墳の中で最古と考えられています。石室は開口していましたが、入り口は土砂でほとんど埋まっています。


重清城に到着!重清城は標高100mの段丘上に位置します。主郭の西側は急な崖で、その自然地形を防御機能として利用しています。
主郭の東側から北側にかけて二重の堀と土塁がつくられ、現在でも往時の姿を見ることが出来ます。徳島の中世城館の中では遺存状況が非常によく、平成13年に美馬町(現美馬市)の史跡に指定されました。
この城をめぐって、三好氏と長宗我部氏が激しい攻防を繰り返しており、今は崖を樹木や竹が覆っていますが、当時はどんな様子だったのか、どのような戦が繰り広げられていたのか、想像が膨らむばかりです。

最後に、県内最古の博物館「美馬郷土博物館」と県指定名勝で四国最古の枯山水庭園がある「願勝寺」と国指定史跡である「郡里廃寺」を訪れました。博物館と庭園は、願勝寺さんのご厚意で見学することが出来ました。ありがとうございました。
郡里廃寺を訪れたときは、その指定範囲の除草作業が行われており、参加者のみなさんも思ったより広い寺域に驚いていました。
今回、大型バスが入らないところがメインとなり、1万2千歩以上歩くツアーとなりました。参加された方々もその日の晩はよく眠れたのではないでしょうか。
アワコウコ楽倶楽部のメンバーも、これまでと同様に準備や説明、誘導などで大活躍しました!
ケガや事故もなくスムーズにバスツアーの進行が出来たのは、参加された皆様、アワコウコ楽倶楽部のメンバーさん、快適な運転をしていただいた運転手さんのおかげです。ありがとうございました 。
来年度も皆さんに楽しんでいただけるような、バスツアーを企画していきたいと思います