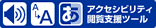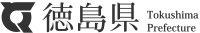出張展示「銭 発掘!」
アワコウコ楽デリバリー展示「銭 発掘!」ただいま開催中!
古代中国やローマの貨幣から、古代・中世を経て、江戸時代の金銀貨まで、県内の出土品を中心に約4,500点もの銭を展示して、お金の歴史がわかります。(一部、個人の収集品も含みます)
また徳島県立埋蔵文化財総合センター「レキシル徳島」でできる体験メニュー「鋳造体験─お金を作ろう─」もご紹介。
- 場所徳島県庁1階 県民ホール
- 期間平成27年12月18日(金)まで。(最終日は午前中まで)土・日は閉庁
- 時間県庁の開庁時間 8:30~18:30
- その他観覧無料。お車でお越しの方は県庁駐車場にとめて、駐車券は1階受付にて押印して下さい。

寺山遺跡出土の埋納銭3,715点、レプリカと出土品

お金の歴史が一目でわかります。

右から、古代中国の貨幣。お金の始まりは貝貨(南の海で採れるタカラガイ、展示品は現代のもの)で、「財」や「買」という字に「貝」が入っているのもそのためです。
その後、武器や農具を模した形のものが登場し、やがて円盤に四角い穴を開けたものに落ち着きました。
中央には古代ローマのコイン(個人収集品)、左にはわが国最初の流通貨幣である皇朝十二銭のうち、県内の遺跡からの出土したものを展示。

中世のわが国が、中国との貿易で大量に輸入した銭。室町時代には国内で品質の悪い銭が大量に作られました。

貨幣制度が統一された江戸時代。金・銀・銅の3種が使われました。しかし、財政が傾くにつれて金銀の質が悪化したり、小さく軽くなったり、安価な鉄銭も作られました。また、各藩が独自に発行した「藩札」という紙幣まで登場しました。
なお、小判は模造品です(^^;)

県内から出土した埋納銭─埋められた銭─です。写真は海陽町大里出土銭で備前焼大甕に70,088枚、展示品は小松島市根井の出土銭(個人蔵)で備前焼の壺と出土銭の一部を展示しています。レプリカとともに出土品を展示しているのは寺山遺跡の埋納銭。発掘調査で埋められた当時の状態で見つかりました。銭は97枚前後でひとくくりしています。これが当時100文で通用しました。

吐気山古墳(吉野川市)の墓から出土した皇朝十二銭、中庄東遺跡(東みよし町)からみつかった地鎮祭の跡。お金に託した想いや願いが見えます。
左にあるのは徳島県立埋蔵文化財総合センター「レキシルとくしま」で体験できる鋳造体験「お金を作ろう」のご紹介。体験はイベント時に実施しますので、こまめに情報をキャッチして下さいね!

お金に興味があるみなさま、ぜひぜひ県庁まで足をお運び下さいm(_ _)m