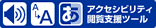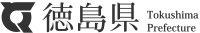黒谷川郡頭遺跡の調査成果について
平成 23 ・24 年度に公益財団法人徳島県埋蔵文化財センターが調査した黒谷川郡頭遺跡の発掘調査成果がまとまったので、概要について以下のようにお知らせします。
平成 23 ・24 年度に公益財団法人徳島県埋蔵文化財センターが調査した黒谷川郡頭遺跡の発掘調査成果がまとまったので、概要について以下のようにお知らせします。
- 遺跡名黒谷川郡頭遺跡(くろだにがわこうずいせき)
- 所在地板野郡板野町大寺字山田畑
- 調査面積のべ面積 2,465平方メートル
- 調査期間平成23年11月1日~平成24年3月31日
- 平成24年4月1日~平成24年8月31日
- 調査原因吉野川下流域農地防災事業(大寺工区)関連埋蔵文化財発掘調査業務
黒谷川郡頭遺跡 調査区全景
主な成果
弥生時代前期(前4~前3世紀)と後期~終末期(2世紀~3世紀)、奈良時代~平安時代(8世紀~10世紀)の集落跡を確認した。
弥生時代後期~終末期の集落跡では、竪穴住居 12 軒や区画溝などを確認した。
黒谷川郡頭遺跡で、これまでに見つかった弥生時代後期~終末期の竪穴住居は30棟を上回る。これは県内の同時期の中でも最大クラスの規模である。
今回の調査で発見された竪穴住居で最も大きいものは、長径9.1メートルの規模をもち、平面形態が六角形となる特徴がある。
黒谷川郡頭遺跡 平面形態が六角形の竪穴住居
出土品は土器・石器など十万点を超える。出土品の中には蛇紋岩製の勾玉や水銀朱を精製するのに用いる石臼や石杵が含まれる。
- 黒谷川郡頭遺跡区画溝から出土した土器の様子
- 黒谷川郡頭遺跡土器の発掘の様子
- 黒谷川郡頭遺跡勾玉の出土の様子
竪穴住居の構造上の特徴(平面形が多角形、炉が「|○」の配置をとる)は、播磨地域に多く見られるものと共通しており、同地域との濃密な交流を窺わせるとともに、阿波地域において対外交渉の窓口として機能した集落であることが追認された。
問い合わせ
公益財団法人 徳島県埋蔵文化財センター
awapac@tokushima-maibu.net
電話 088-672-4545
ファックス 088-682-4550