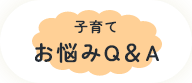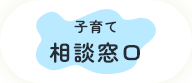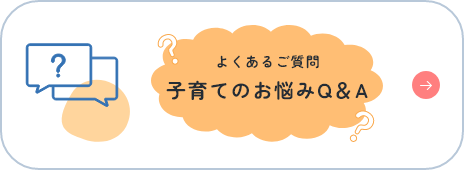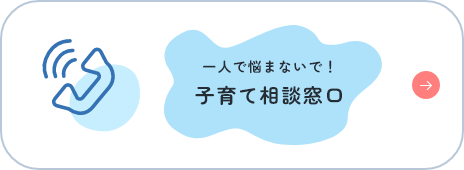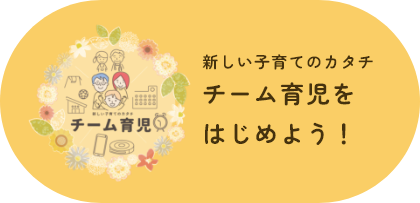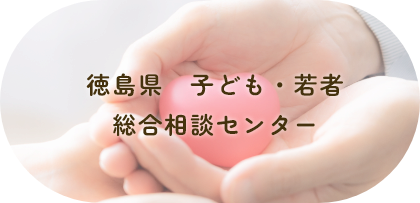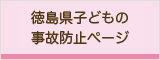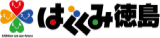令和5年度 第1回地域子育て支援 ネットワーク研修会(報告)
日時
令和5年6月22日(木)13:00~16:00
場所
徳島市山城町東浜傍示1-1
徳島県立男女共同参画総合支援センター 2階 学習室
参加者数
42名
「感覚統合から見た『気になる行動』の理解と支援」
講師:冨樫 敏彦さん
(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業所トモデココ顧問)


子育て支援者としての専門的な見識を深めるとともに、各子育て支援関係者が互いに必要な情報を共有し、子育てを地域全体で支え合う仕組みづくりを共に考える機会とすることを目的に「地域子育て支援ネットワーク研修会」を開催しました。今回は、教育・医学両面の研究に精通された冨樫敏彦さんを講師にお招きし、気になる行動には原因があり、原因を分かるために感覚と行動の関係を知り、療育・支援の仕方を具体例と体験を通して学びました。
講演
つま先立ちで歩く、その場をくるくる回る、嫌なことがあれば自分を叩く。指示が聞けない、10人いれば10人が違う。子どもをどのように育てていけば良いのかがスタートライン。
気になる行動には理由があり、親や先生を困らせるような顔をすること事態に原因がある。怒ると効く場合もあるが、怒られる人の前では効いているが、違う場面でまたおこる。モグラたたき状態である。原因がわかってそれを直さなくてはいけない。
原因がわかるために行き着いたのは、気になる行動は、感覚統合という一つの考え方からどのような療育、支援をすればよいかがわかってくる。
気になる行動の事例
- 光りを眩しがる
- 触られること・汚れることを嫌がる
- 散髪・帽子をかぶることを嫌がる
- 振動する物が好きで触る
- 圧迫される狭いところが好きで入る
- 指を引っ張ってもらうことを求める
- 偏食がある
- 何でも匂いを嗅ぐ
- すぐに疲れたと言う
- 原因が分からない泣き笑いがある
- 季節によって調子が悪くなる
感覚統合がうまくいっていない状況とは
参加者が2人組になって「気になる子」の体験をする。(de Quirusの実験より)
- じゃんけんで勝ち・負けを決める。
- 2人は1m離れて立つ。
- 負けた人は片足立ちをする。勝った人は人差し指を立て2秒に1回、腕をくるくる回す。
- 負けた人は、片足立ちをしながら、くるくる回る指先を見る。
- 勝った人は腕を回しながら、繰り上がりのある2桁+2桁の足し算を言う。
- 負けた人は、片足立ちをしながら、目で追いながら2桁+2桁の足し算の答えを言う。
負けた人は4. の動作の片足立ちをしながら、くるくる回る指先を見ることはできる。
⇩
皮質下だけで処理できるから
しかし、6. の片足立ちをし、くるくる回る指先を見ながら、繰り上がりのある2桁の計算はできない。計算をすると指先を目で追えない。指先を目で追うと計算ができない。(皮質下だけでは無理。)同時に二つのことをしようとすると、脳全体が精いっぱいとなる。
「姿勢を良くしてこっちを向いて。」も姿勢を良くすることと、こっちを向くことと二つを同時にしなければいけないので、やはり脳全体がいっぱいとなりできない。「眼球運動」や「姿勢・バランス」が皮質下で、無意識に処理できるようになると大脳皮質は空いているので、考えることに集中でき、読み書き・計算ができるようになる。
うまくできない状況を把握し、眼球運動やバランスを育てる活動を行い、意識せず無意識に処理できるようにする。
気になる行動の原因と対策
【視覚過敏】
光を眩しがる視覚と聴覚に過敏性が見られる子どもには、どのように周りが見えているのか、動画を視聴し確認する。(川崎市立小杉小学校の映像)
映像では、採光が教室に入り、鏡が反射しているかのように眩しく見えている。
机の上に置いていたコップの水をこぼした子どもの、荒い息づかいが音声から聞こえる。
映像の中では、過敏症の子どもの映像はなく、周りの人のみ映されている。指導者らしき人がこぼれた水を拭き、優しい口調で語りかける。「大丈夫よ。びっくりしたね。あっちの席に移動しようか(別の部屋に移動)さっきはびっくりしたね。ここなら大丈夫。」と子どもを落ち着かせた。
視覚過敏かなと思ったら……
- ブラインドやカーテンで部屋の光を調整する。
- カーテンの隙間から床に差し込む光にも注意が必要。
- 座っている席の位置にも配慮する。暗い所と明るい所のコントラストが一番厳しい。
- 色のついたメガネをかける。
【光による睡眠障害】
季節によって、目の中に入ってくる光の量が変わる。光の量で睡眠障害が起こり、角錐リズムが狂う。光の量によってメラトニンのコントロールができなくなる。季節の移行期である春から夏、秋から冬は、(日照時間の差により)行動のコントロールができず、興 奮状態や多動性になりやすく、落ち着かない。
周りの人は、環境の変化を把握し、行動の原因を知ることも大切である。
【聴覚過敏(音に敏感)】
何の音が嫌いなのかは、個々によって違う。歯医者で歯を削るような音が発生する。
物理的に音を小さくする……
- ノイズキャンセリング耳栓(周囲の不快な音を消す効果がある)
- イヤーマフ
我慢することを覚える……
- 例えば、赤ちゃんの泣き声が苦手な子どもは、音(赤ちゃんの泣き声)が出る理由を理解し、我慢することを覚える。
[お腹が減ったら何か食べたいでしょ。赤ちゃんは、お腹が減ったら「ミルクが飲みたいよ」と泣くよ。お母さんがミルクをあげると泣き止むよ。だからミルクをもらうまで、ちょっと我慢しようね。]
クワイエットアワー(静かな時間)の取り組み
感覚過敏の子どもにとって、買い物は試練である。音や光によってパニック状態となり、大声をだしたり走り回ったりして行動は落ち着かない。周りからは親の躾がなってないと、冷たい目で見られる。
このような子どもの支援として、イギリスでのクワイエットアワーの取り組みを映像で視聴する。取り組み前でのショッピングモールでは、パニック状態で走り回っている子どもの映像が映り、取り組み後では、照明を暗くし、音楽を鳴らさない。そのため、光や音を怖がらず、おもちゃ売り場で買い物を楽しんでいる様子が分かる。
このような感覚過敏の子どもに配慮した取り組みが、日本でも始まっている。
2023年「かわさきパラムーブメント」と「東急ストア」がクワイエットアワーを実施する。
まとめ
見た目には分かりにくく、 自分自身も過敏症であることに気づくまでに時間がかかる。周りの人はできるのに、どうして自分はできないのか… と自分を責め、劣等感の塊で孤独に過ごすことも多い。スポーツを楽しむ前に諦める。 生きづらさを感じつつ 周りに遠慮しながら生きている人もいる。
▼
▼
▼
川崎市立小杉小学校の動画の中で、P K をしているクラスメートの子が、発達障害の子どもに対して、もしよかったら P K を一緒にやろうと誘い、ルールを優しく説明し、手本を見せている。合理的配慮で、孤立しがちな子どもに対しての思いやりが見える。
気になる行動には原因があることを知り、原因を突き止める手立ての一つである感覚統合を理解し、解決できるよう支援しなければいけない。スポーツを楽しみ、友だちと楽しい学校生活を送り、自由に買い物ができる 当たり前に生活したいという思いを周りはしっかり受け止め、理解と認知 で一人ひとり全ての人が、快適な生活ができ、互いに助け合うことが大切である。
感想
- 気になる子どもの行動には、 意味があることを理解し、 保護者や家族、担当課と協力し、療育に繋げられる支援をしていきたい。
- 姿勢を正しくする、 目線を先生に合わせる、 話を聞くの3つを同時にすることの難しさを理解していなかった。自分にとって当たり前のことが、難しい子どもがいることを知り、 今後は、気になる行動をする子どもへの配慮もしっかりしていきたい。
- 光の量によって生活が困難になることを初めて知った。
- 理論と実際の子どもの見方や改善するための関わり方について、具体的に教えていただけたのでよかった。
- 様々な過敏の症状の人がいることが分かった。「何にでも原因がある」と言うことを改めて考えることができた。
- 脳の発達、体の発達の成り立ちがよくわかった。一つの動きから全てが繋がっていることが理解できた。
- 様々な年齢の成長過程の観察どころを伝えてくださり、日常に非常に役に立ちそうだ。また、イギリスの事例を360度見られる動画は、それぞれの立場で考えられるので、非情にありがたい。
- 「気になる行動には意味がある」 と言うことを裏づける講演だった。検診時の相談や面接の時に話せる内容が変わってくると思う。 遠城寺式で発達検査をしているが、成長発達の過程を知ることができた。 自分の身体の辛いところを治す、守るための行動なのだと思った。もの凄くいい研修だった。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課