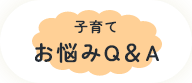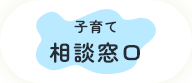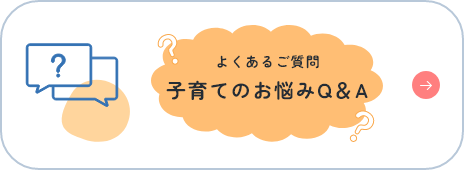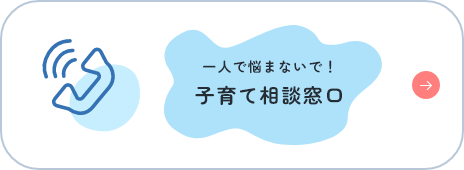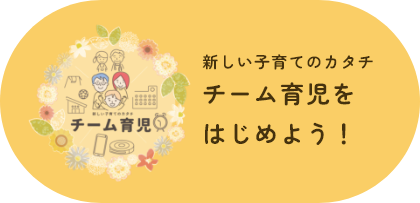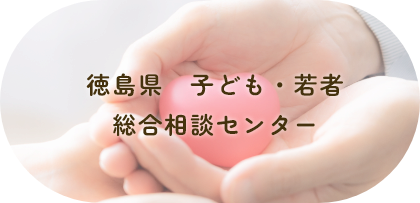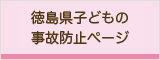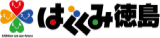令和4年度 第3回 被災児童保育ボランティア養成講座(報告)
日時
令和4年9月16日(金)13:00~16:00
場所
徳島市山城町東浜傍示1-1
ときわプラザ学習室(アスティとくしま2階)
参加者数
26名
その他
本講座は、検温、換気、マスク着用、手指のアルコール消毒、会場内の消毒など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて開催
「特別な配慮を要する子どもへの支援」
講師:前田 宏冶さん(四国大学生活科学部児童学科教授・学修支援センターセンター長)


【研修会の目的】
- それぞれの障害の特性を理解し、災害時、支援が必要な子どもたちに対する支援の在り方について学ぶ。
【自閉スペクトラム症】の具体的特性
- 偏食障害・睡眠障害
…蒸しパンには虫が入っているから食べられない。異食(砂・リップクリーム・自分の糞尿等)本来食べられないものを食べる。 - 感情のコントロールができない
…わがままと捉えられるが自分の心の内が言えない。
どう表現していいのかわからない。
言葉で説明するのは難しい。
「どうして○○したの。?」では答えられない。
行動にはそれぞれ理由がある。 - 五感が過敏
…うるさい・怖い・臭い等。
通常なら感じないほどのものでも、実際に体に触られるのを嫌がるなど身体的不快を顕著に感じる。
音への過敏な反応が大きなストレスになっている。 - 鈍感
…怪我をしているのに気がつかない。
空腹感・満腹感に気づきにくいため、過食や低血糖になり易い。 - 拘りがある(避難生活は苦痛でしかないので最大の問題)
…書かれたものに従うことに強くこだわる。
ルーティンが決まっているので急な予定変更などはパニックに陥る。 - コミュニケーション障害
…ちゃんと・きちんと・しっかり・適当に・いつでも・だいたい。
⇩
曖昧ないい方では通じない。 - 常識・当たり前はわからない
…当たり前だと思っていることも言葉が足りなくて通じない。 - トラウマになり易い
…写真的記憶・忘れられない・断片的な記憶・フラッシュバック・タイムスリップ。
聴覚的記憶は弱い。
強いトラウマ体験を受けた場合に、後になってその記憶が突然かつ非常に鮮明に思い出されたり夢に見たりする。
★★このような特性を理解した上でどう支援していけば良いのか★★
○偏食障害・睡眠障害では
- 不安材料は丁寧に説明する(蒸しパンには虫が入っているわけではない等。)
- 食への関心、食べたいという気持ちを育て、ある食材が楽しみになることで他の物を触ったり、舐めたり、 チャレンジする心を育てる。
- 好きな物を食べ過ぎたり、拘りに合わせ過ぎたりするとチャレンジする気持ちが失われるので空腹の方が良い。
- 安心して食べられる環境作りをし、食べられるものを揃え、食への不安を取り除く。
- 選択が可能であれば自分で選んだものは食べられる。
- 発達に合わせた対応の必要性とこの人となら頑張ろうという気持ちを育てる。
- ASD児は 腹痛・腹部膨満感・便秘・下痢・嘔吐・嚥下困難の胃腸症状が多く、睡眠の問題にも関連している。そのため食べない、 飲まない、眠れない等の問題も起きやすく、避難所ではすぐに駆け込めるよう、トイレの確保・清潔が大切。
○感情のコントロールができない
- 行動には理由があるので、周りがわがままではないと理解し、受け止める。
- 会話の見える化をする。→吹き出しなどで会話する。(コミック会話)LINE ,iMessageなど
- 理由ではなく、「何があったの?」と状況を尋ねる。→写真的な記憶の中で説明できる。
- 行動に着目しABC分析をする。
- A:どんなときに➔直前の状況
- B : 何をすると ➔行動
- C : どうなったか➔結果
- 時間がかかることを理解する。


○五感が過敏・鈍感
- 多様な触覚情報に楽しく触れることのできる環境設定や支援を行うことが不可欠。
- 汗はかいたがシャワーを浴びると体が痛くてシャワーが使えない人もいることを支援者が知っていることも大切。
- 明るさに敏感な場合はサングラスをかけるなどアドバイスする。
- 大きな声や身体接触に過敏な子には、穏やかな表情・穏やかな声で「手をつないでもいい?」など予告説明をする。
○拘りがある
- 予定をコロコロ変えない。やむなく変える場合は早い段階で変わった内容を相手が理解するまで言い続ける。
- サポーターフックやヘルプマーク (本人の障害や対処法・連絡先等)を書いたものを身につける。
- 苦手なことを無理に克服させようとしない。
- 苦手なことは避けて通る。
- 失敗を責めない。
○コミュニケーション障害
- 出し方はCCQ
- Calm (あなた自身が穏やかに)
- Close(もう少し子どもに近づいて)
- Quiet(声のトーンを落として静かに)
- 内容はCCS
- Clear (明瞭に)
- Concrete (具体的に)
- Short (短く)
- 支援ボード等の絵を使うことによりコミュニケーションがスムーズにいく。
○トラウマになり易い
- ストレスを感じにくい生活習慣や環境を整える。
- 理解し受け止める。返してあげるだけで、この人はわかってくれるという安心感につながる。
被災した特別な配慮を要する子どもへの支援
グループワーク(グループで話し合い、意見交換を模造紙にまとめていく)
【グループの発表】
- 支援者が情報を共有しておく。
- 子どもがひとりにならないよう観察する。
- 支援者も同じ被災者であることを知ってもらい寄り添う。
- 子どもが怖がらないよう、何ものかをわかってもらう。
- 行政の力を借りる。(物資・トイレなど)
- 個人のスペースの確保をし、プライバシーが守られるように努める。
- 専門家の派遣で知識・経験を得る。
- 子どもだけでなく家族との理解を深める。
- 子どもの喜びそうな絵本やおもちゃの手作りをし、仲良くなる。
【講師のまとめ】
✫外見から障害のあることが判断しにくい子どもたちは、周囲から理解されにくく、不適切な行動を親の躾のせいにされ、保護者が大変苦労したという事例がある。障害があることや適切な対応の仕方を避難所で共に生活する人たちに知ってもらう必要がある。
事例
2年前の夏,大雨による避難勧告が長崎市に発令された。コミュニケーションなどが苦手な自閉症スペクトラム障害(ASD)の幼い子どもをもつ20代の母親は避難するかどうか迷った。
コロナ禍での避難で住民も神経質になっているはずだった。「 うちの子は感覚過敏でマスクをつけることができない。大声を出したり、走り回ったりするだろう。避難所での周囲の冷たい視線に私自身耐えられるだろうか…。」親子は結局、自宅近くの避難所に行くのを諦め、ホテルに連泊した。そこでも狭い空間で体を思うように動かせず、大きなストレスを感じていたという。
長崎県自閉症協会によると、災害時の避難は共通の悩みや心配事であり、「避難所で(周囲に)迷惑をかけたくない。」と考える会員も少なくない。2016年の熊本地震では体育館など公共施設への避難を諦め、車中泊や軒先避難を選んだ発達障がい者やその家族が数多くいたという。
*出典:長崎新聞2022年3月17日 「 避難所も『誰ひとり取り残さない』発達障害児らとその家族対応機運高まりに期待」
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課