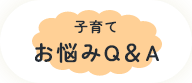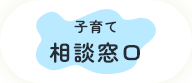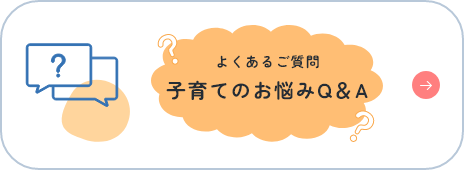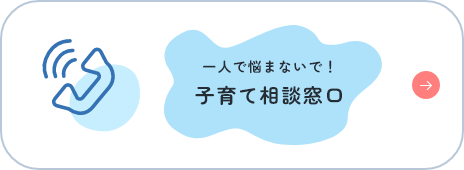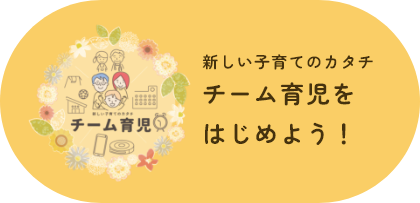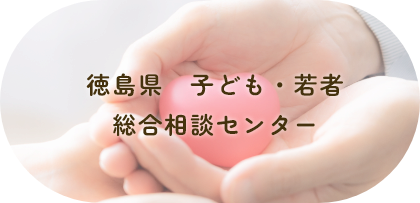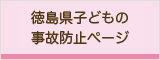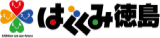令和4年度 第2回 被災児童保育ボランティア養成講座(報告)
日時
令和4年8月16日(木)13:00~16:00
場所
徳島市山城町東浜傍示1-1
ときわプラザ学習室(アスティとくしま2階)
参加者数
24名
その他
本講座は、検温、換気、マスク着用、手指のアルコール消毒、会場内の消毒など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて開催
「大規模災害後の子どものメンタルヘルスサポート」
講師:松本 有貴さん(徳島文理大学人間生活学部児童学科教授)


被災後の子どものトラウマについて理解し、支援者のセルフケアの重要性について、グループワークを交えながら学びました。
【研修会の目的】
- 被災後に児童・生徒に現れやすい反応を理解し、被災後の支援に対する自信を高める
- 職員のセルフケアの重要性を理解する
- サポートを必要とする子どもを特定し、相談窓口へつなぐ
〈被災児童保育ボランティアの役割〉
あたたかさ・ここちよさ = 安全基地機能
安全・安心を感じる環境が整うと、子どもは個人の力が発揮できる。また、安全を感じて人と交流することは、人生の質を決定づけると言われている
被災状況下において、安全基地機能を提供することが一番の支援となる
↓
児童が、「助けて」と言えるようになる支援ができることが重要
〈被災時の子どもの反応〉
一人一人の背景が違うことを慮ることが重要
「困った子どもは、困っている子ども」として捉えてあげる
●子どもの認識
- 子どもの反応はどう脅威を認識したかに左右される
- 子どもの脅威の認識は大人とは異なる
- ほとんどの子どもは6ヶ月で回復する
- 10%の子どもは特別な支援が必要
★災害時、心理的支援のまずすることを4つの課題に分け、グループで話し合った
- 普段どおりの生活習慣をまもる
- 安全を確保する
- 聴き、話し、遊ぶ
- 大切な人と遊ぶようにする
〈支援者ができること〉
災害後の支援者の役割
- 子どもにとって良い大人であり続ける
- 子どもを生活面や教育面で支え続ける
- 災害時に起こりやすい反応、それが及ぼす影響を把握する
- 関係機関と連携
★安心・安全な関係・環境と整えることを3つの課題に分け、グループで話し合った
- 取り組めること
- 期待する成果
- 課題(難しさ)
〈支援について〉
TIC(トラウマ・インフォームド・ケア)=トラウマについて知ってケアすることが重要
TICの前提となる基本「4つのR」
- Realize:理解する
- Recognize:認識する
- Respond:対応する
- Resistre-traumatization:再トラウマ化を防ぐ
TICの実践に必要な「6つの主要原則」
- 安全・・身体的、心理的な安全性、安全な関係性を保つ
- 信頼と透明性・・組織運営や意思決定を見えやすくわかりやすくする。
- ピア・サポート・・トラウマの実体験を持つピア(仲間)による相互自助を活用
- 協働と相互性・・支援する人、される人の双方が意見を言い、尊重し合う
- エンパワメント・・支援される人自身が選択できるようにかかわる
- 文化・歴史ジェンダーへの配慮
〈支援者のセルフケアについて〉
被災児童を支援する、笑顔で聴くには、エネルギーが必要 → 支援者のセルフケア
●支援者は共感能力が高く、自分がつらくなる=共感疲労
自分の事は後回しになり、疲れ果て、トラウマ的なストレスになる
↓
セルフケアが重要
〈セルフケアの方法〉
- ストレスに気づく
- ストレスや情緒反応を適切なレベルに下げる → ストレスはなくならない
- 適切な対処方法を実践する
方法は呼吸法や、健康的なライフスタイルの維持等色々あるが、トラウマ的なストレスを抱えていない子どもと時間を過ごすことも対処法となる
★セルフケアに計画についてグループで話し合った
- 自分のストレスサインを知ってますか?
- あなたのストレス解消法は何ですか?
- 相談相手がいますか?
〈情報収集について〉
- 守秘義務を遵守しながら、当人と話し合いをもつ
- 守秘義務を遵守しながら、保護者から情報を得る
- 子どもの懸念点について、保護者も同意見であるかを確認する
- 相談機関に関する情報やアドバイスを提供する
〈相談機関につなぐタイミング〉
- 症状が持続、または悪化
- 学業の深刻な低下
- 問題行動が日常的に起こり、深刻な心理的苦痛を伴う
- 感情のコントロールが困難で、持続または悪化する
- 社会的機能の深刻かつ長期的な変化が見られる
↓
園や学校の情報資源や地域のサービス等につなぐ
★子ども(5歳)の事例を挙げ、グループで話し合った
- どのような精神的苦痛のサイン・反応が現れてますか?
- どのような追加の情報が必要ですか?
- 支援者として、今あたなができることは何ですか?
- 連携する専門家・専門機関は?
参加者の感想等
- 被災児童保育ボランティアの役割=温かさ・心地よさであることがよく理解できました。
- いろいろ具体的に教えていただき、多くの人の考えも聞けて充実した時間でした。
- 被災をした場合の実際をより分かりやすく講義していただいた。自分ももっと本格的に考えていきたいと思う。
- 思いつかない事柄を知ることができました。
- 子どもにとっての安心は、普段からの信頼関係を築いていることが大切だと思いました。
- 児童を観察し変化に早く気づいてあげることが大切だと思いました。
- メンタルケアは自分自身にも必要であることがわかりました。出来ることから始めるのが良いということもわかりました。
- 被災はいつ起こるかわからないので、色々と勉強になりました。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課