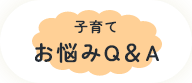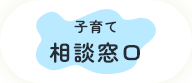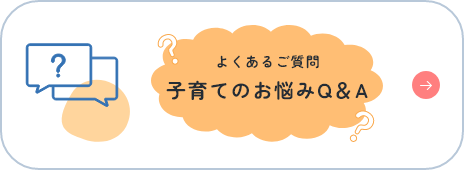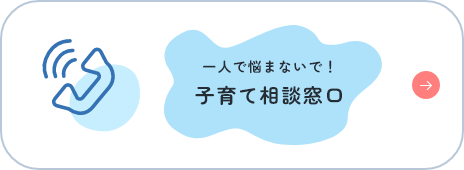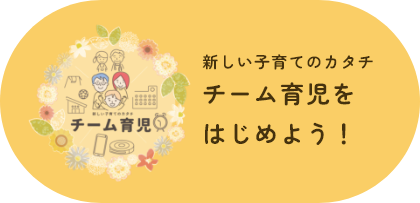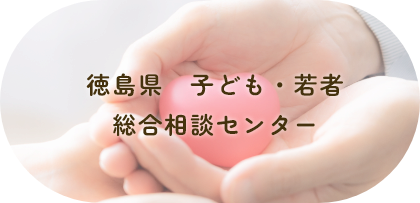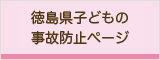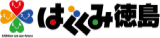令和4年度 第1回 被災児童保育ボランティア養成講座(報告)
日時
令和4年7月8日(金)13:00~16:00
場所
徳島市山城町東浜傍示1-1
ときわプラザ学習室(アスティとくしま2階)
参加者数
29名
その他
本講座は、検温、換気、マスク着用、手指のアルコール消毒、会場内の消毒など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて開催
「避難所における感染対策」
講師:藤田 洋子さん(徳島県立海部病院 感染管理認定看護師)


感染症対策について、ゴミ袋を使ったビニールエプロンの作成等のワークを交えながら学びました。
【感染症対策の基礎知識】
感染症とは病原体が体に侵入し、症状が出る病気のこと。
感染経路には、垂直感染と水平感染がある。
- 垂直感染とは妊娠中、出産の際に赤ちゃんに感染すること。
- 水平感染とは接触感染、飛沫感染、空気感染、媒介物感染に分類される。
- 接触感染 感染者に直接接触して感染
- 飛沫感染 咳やくしゃみで飛び散った飛沫を吸い込むことで感染する
- 空気感染 空気中の粒子を吸い込むことにより感染
- 媒介物感染 汚染された水、血液、昆虫などを介して感染
感染成立の3要因・・感染源、感染経路、宿主の3つの要素がそろうこと。
感染対策は、3つの要因のうちひとつでも取り除くことが重要。一番簡単なのが感染経路の遮断として手洗いである。
感染成立の3要因への対策・・「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」
ボランティアに参加する際は、事前から感染症予防を徹底し参加することが重要
ボランティアの参加者ができることは標準予防策と感染経路の遮断
↓
1.手洗い 2.個人防護具 3.環境整備(掃除)
〈標準予防策〉
1.手洗い・・石けんと流水、アルコール手指消毒の2種類ある。
手荒れは感染リスクが高まるので、ハンドケアも重要である。
石けんと流水 → 目に見える汚染がある場合の方法。 手順どおり洗い、ペーパータオルで拭き取る。 指先、手首、指の間等の洗い残しを意識すること。
●グループ(5~6人)で石けんと流水による手洗いのワークを実施
1名に手洗いをしてもらい、ペーパータオルできちんと拭き取れているかを調べた。
方法として、ごまの入ったビニール袋に手を入れてもらい、ごまがどの場所にどれだけついたかを絵に表し発表した。しっかり拭き取ることを確認した。
●各自アルコール手指消毒のワークを実施。
アルコール手指消毒剤 → 目に見える汚染がない場合の方法
十分な量をしっかりとすり込む様にすること
2.個人防護具の着用・・手袋、マスク、エプロン、ゴーグル等
血液、体液、分泌物、排泄物等のはね返りの予防に有効
脱着する時に気をつける。手袋はできるだけサイズの合ったものを選ぶ。サージカルマスクは防御率が高いので効果的である
●ゴミ袋を使ってビニールエプロンを作成、脱着するワークを実施。
マスク、手袋、作成したエプロンを使用し、付け方、外し方の順番等を確認した。
〈感染経路の遮断〉
- 接触感染予防策
接触感染とは、感染者と直接、または、汚染された物や人を介して間接的に接触することで感染すること。予防策として、手袋、ゴーグルなどの個人防護具を使用。 - 飛沫感染予防策
飛沫感染とは、咳やくしゃみ、会話などの際に飛び出す5μmより大きい飛沫が目や鼻、気道の粘膜に付着することで感染すること。予防策として、サージカルなどの個人防護具を使用。 - 空気感染予防策
空気感染とは、口から飛び出した飛沫の水分が蒸発してできる5μm以下の飛沫核が長時間空気を浮遊し、これを吸引することによって感染すること。
予防策として、医療従事者はN95マスク、患者はサージカルマスクなどの個人防護具を使用。
※ワクチンの接種歴を記録に残すことを推奨する。
〈環境整備〉
共有する物等の管理が重要
↓
ウイルスによっては、かなり長期間生存している場合もあるので、手がよく触れる環境表面をアルコールで消毒する。
(ドアノブ、手すり、ボタン類、ペーパーホルダー等)
●グループで、効果的な環境整備、掃除の方法についてワークを実施
普段のふき掃除の仕方について、ウェットティッシュを使って机のふき方を考えた。
グループ毎に発表し、それに対して講師にアドバイスを頂き、正しいふき方を確認した。
アドバイスの内容
- アルコールを机に吹きかけるはタブー。吹きかける際に、飛散し、それを吸う恐れがあるため。→ ペーパータオル等に染みこませ、机を拭く。
- ふきんは使い捨てが好ましいが、コスト的に難しい場合は、複数用意し拭く範囲を決める。
(例:Aは左3列、Bは中3列、Cは右3列等) - ふきんを使用した後は、洗濯し、乾燥機や日光干すること。
→ 熱や紫外線を当てしっかりと乾かし、雑菌の繁殖を防ぐ。 - 避難所ではルールを決めて、誰が行っても同じ方法とすること。
→ 不特定多数で関わる場合、共有できる記録物を示すことが重要。 - 消毒液は光に弱いので、屋外に置くとアルコール効果を失うことに気をつける。
- 清潔な面から一方向に向かって拭く。→ 面を変えて一方向に拭く。
【災害に関連した感染症】
- 〈頻度が高い感染症〉
- 風邪、インフルエンザ、感染性胃腸炎
- 外傷に関連した感染症 → 破傷風、創部感染
- 津波関連の感染症 → 誤嚥性肺炎、津波肺
- 血流感染
- 〈避難生活で問題となる感染症〉
- 経口感染・・感染性胃腸炎、ウイルス性肝炎等
- 接触感染・・黄色ブドウ球菌感染症、疥癬等
- 飛沫感染・・インフルエンザ、肺炎球菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎
- 空気感染・・結核、麻疹、水痘
↓ 予防
- こまめな手洗い、うがいの励行
- アルコール手指消毒剤の確保
- 食べ物の管理・症状がある方は、個別の待機場所、導線、トイレの区別
- 初動対策が最も重要
- 〈感染症を流行らせないために環境を整える〉
- 定期的な換気と衛生環境を整えた導線
→ 入口と出口の分離、生活の場とトイレの分離 - こまめな手洗いやうがいができるように物品の調達
- 口腔内の清潔を保つ → 洗口液、歯磨きできる環境
- 食べ物の管理 → 残った物は捨てる等
- 相談窓口の設置
- 定期的な換気と衛生環境を整えた導線
- 〈感染症防止のために決めた方がよいルール〉
- 全ての人にマスク着用(新型コロナウィルス感染症流行時)
- 手指消毒の徹底
- 水分補給
- 人と人の間隔の確保
- 体温、体調の管理
- 清掃当番(トイレ掃除)を決める
- ゴミを密閉して、決められた場所に廃棄
- 靴はビニール袋に入れて各自保管(土足厳禁が望ましい)
- 洗濯は、家庭ごとに行うことを徹底
- 〈避難所生活 その他の予防〉
- 慢性疾患の悪化予防(薬の手配)
- エコノミークラス症候群予防(血栓を防ぐ)
- 生活不活発予防(体操の推奨)
- 熱中症予防(夏)
- 低体温症、一酸化炭素中毒(冬)
- 口腔衛生管理
- アレルギー疾患の悪化予防
【避難所に関連した感染対策】
- 〈感染対策7つのポイント〉
- 正しい手洗いの励行とうがい
- 入口・トイレなど感染対策ポスターの掲示
- 咳、くしゃみが出る人への咳エチケットの徹底
- 感染症伝播が起こりやすい共同トイレの衛生維持
- 居住区のスペースの確保とストレスへの対応
- 感染症罹患者の把握と対応の徹底
- 清潔な食品管理と食品衛生の徹底
- 〈避難所での居住環境、衛生環境等〉
- 換気の徹底
- こまめに水分補給ができる環境づくり(特に高齢者は脱水症になりやすい)
- 室内は土足厳禁とし、通路を確保する
- ゴミを捨てる場所を定め、捨て方を徹底する(密封する)
- 生水は避ける
- 普段から食べ慣れているお菓子を日頃から準備する
- 食事をため込まない
- 症状がある人は食品を扱わない
- トイレはできるだけ男女に分ける
●グループで、正しい体温測定についてワークを実施
- 〈グループの意見〉
- 複数回実施する
- 機器により誤差がある
- 測定する部位を変えて、測定する
- 距離感に気をつける
- 汗を拭いてから測定する
- 〈講師回答〉
- 体温計により部位・計測時間が違う → 取扱い説明書に従う
- 非接触型体温計は赤外線で測定しているので、屋外は不向き
【新型コロナウィルスの概要】
- 〈特徴〉
- アルコールで失活する。変異を起こしやすい。
- オミクロン株は、咽頭痛を訴える人が多い。人によっては、鼻づまり、鼻水、頭痛を訴え、多種多様である。
- 肺塞栓、血栓症との関連性が深いことが報告されている。
- 基礎疾患があると致死率が高い。
- 問題になっているのは罹患後症状 → すっきり治らないのでフォローが必要。
- 飛沫感染がメインで接触感染、エアゾル感染でも伝播する。
- 〈標準予防策の徹底〉
- 正しくかつ適切なタイミングで手洗い
- 正しくマスクを着用(サイズの選択が重要)
(マスクを2重にして防げるものではない。)
- 〈飛沫感染予防策〉
- 飛沫は人間が発生源かつ飛沫の飛距離はせいぜい2m
→ フィジカルディスタンス、個室隔離 - マスクを着用できない患者、幼児
→ フェイスシールドの着用(目の暴露を防ぐ) - 施設内共有接触面の清掃と消毒が有効
→ アルコール(60%以上)、次亜塩素酸水溶液(0.05-0.1%)
定期的に実施。消毒剤の噴霧は行わない
床や壁など大掛かりな広範囲の消毒は不要
- 飛沫は人間が発生源かつ飛沫の飛距離はせいぜい2m
講師からのメッセージ
- 病原体を「持ち込まない」、「持ち出さない」、「拡げない」
- 感染経路を遮断すること
- 正しい手洗いと適切な個人防護具の使用
- 環境整備
- 避難所で感染症を流行らせないための環境を整える
- ワクチン接種で感染を予防できるものは接種を推奨
- 自分の抗体価とワクチン接種歴を記録しておく
- 報告、相談窓口の確認
- 感染症対策に必要な情報の共有とファインチームワーク
参加者の感想等
- 全てにおいてとても勉強になった。
- 実技もあり楽しく学ぶことができた。手洗い、ビニール袋のエプロンについて活用したい。
- 記録作りやルール作りが大切だと理解できた。日常生活でも感染対策を実践していきたい。
- ビニール袋を使ったエプロン制作は、備蓄が切れた時などに簡易で役立つと感じた。
- 手洗いは消毒が基本だと理解できた。エプロン制作はこどもたちへ伝えたい。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課