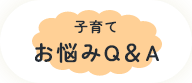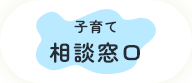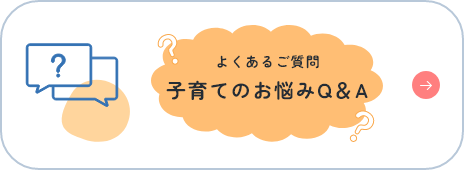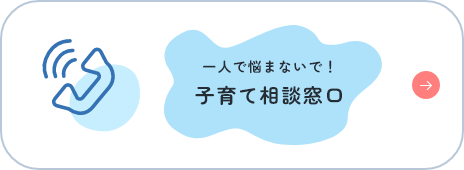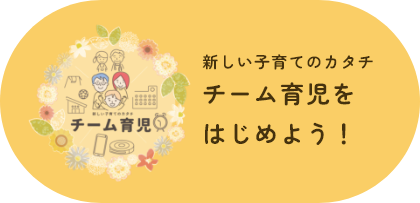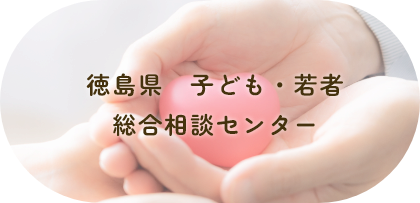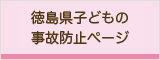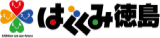令和4年度地域子育て支援ネットワーク研修会
日時
令和4年6月27日(月)13:00~16:00
場所
徳島市山城町東浜傍示1-1
徳島県立男女共同参画総合支援センター 2階 学習室
参加者数
30名
その他
本年度の本講座は、検温、換気、マスク着用、手指のアルコール消毒、会場内の消毒など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じて開催。
「心理面・学習面における子どものつまずきの理解」~心理学を活かして~
講師:金子 紗枝子さん(徳島文理大学人間生活学部児童学科講師)



子育て支援者としての専門的な見識を深めるとともに、各子育て支援関係者が互いに必要な情報を共有し、子育てを地域全体で支え合う仕組みづくりを共に考える機会とすることを目的に「地域子育て支援ネットワーク研修会」を開催しました。今回は、徳島文理大学人間生活学部児童学科講師の金子紗枝子さんを講師に迎え、「心理面・学習面における子どものつまずきの理解」について学ぶとともに、グループワークでは、「コロナ禍における子育て支援」をテーマに参加者で話し合いました。
講演
1 「心理面」と「学習面」のつまずきとは(石隈、1999)
- 心理面(心理・社会面)
子どもの情緒的な苦悩の軽減や自己理解の促進と友人、学級、学校への適応の促進など - 学習面
学習意欲の促進、子どもの学習状況の理解、学習スキルの獲得、学習計画の立案の援助、基礎学力の獲得など。
これらは重なり合い、密接にかかわっている。
2 事例1 ~ ワーキングメモリー ~
算数が苦手な小学5年生のAさん
- 算数のテストの点数がずっと良くなく、「算数は嫌いだし苦手。どうせできない。」と言っている。
- テストを見てみると、単純な計算ミスをしたり、ちょっとした計算や途中の計算過程を暗算でしようとして誤ったり、筆算で位が揃っていないために答えが合わなかったりして間違っていることが多い。
- 本人は「筆算や途中式は書かない。算数が出来る人は書いていないから、書くのは格好悪い」と言っている。
なぜ難しいのか?
音読:文字の読みを思い出す、文の意味を理解する、文を声に出して読む。
単語の記憶
これらを頭の中だけで行わなければならないから
一度にできる作業量は無限ではない(=容量制限がある)から
どうすればよい? 外的な資源を使う
- メモをする
- 誰かに覚えてもらう
- 筆算や途中式を書く
3 事例2 ~ 学習性無力感 ~
勉強に対して、やる気が持てない
- (算数の)勉強は苦手。どうせやってもできない。だから、やりたくない。
- これまでの失敗経験を通して「自分が頑張ったところで、どうせできない。」と考えている。=学習性無力感
- 成功に期待を持てない状態(Seligman & Maier,1967)
子どもへの支援
- 成功経験を積ませる(岡、2012)
- 適度に易しい問題から取り組ませる
- 「自分に力がついてきたからできた」と感じられるようなフィードバックを与える
4 事例3(「発達」135巻を元に作成)
3歳ごろのCさんとDさん
- 些細ないざこざがきっかけで、CさんはDさんを小突いて泣かせてしまった。
- 先生が「Dちゃんの気持ちになってごらん」と諭して、Cさんに反省や謝罪を促した。
- しかしCさんは自分も嫌な気持ちになったことばかり話して、反省したり謝罪したりする様子はない。
子どもへの支援
- 子ども(幼児)に「他者の心の理解」を踏まえた行動を自発的に行うよう求めても難しい場合がある。
- 子どもが他者の心に気付けるよう、大人は他者の心を代弁するような言葉かけが必要。
- 様々な「物語」を通じて、多様な人間関係の在り方を教える。(子安、2013)
5 まとめ
- 社会の変化により(子育て)家庭は様々な課題を抱えていて、それに対する支援が必要
- 同時に子どもも様々な課題を抱えている
- 親への支援、子どもへの支援を行うことと、「親と共に子どもの支援を行うこと」も重要ではないか
- 支援者の専門性は、きっと親の子育てにも役立つ
グループワーク
「コロナ禍における子育て支援について」をテーマに1班~6班に分かれて話し合いました。
話題
- 1班:オンラインでの集まりが難しい。人恋しいのか対面の方が多く人が集まる。
- 2班:コロナ禍でも対面を希望する保護者やオンラインについていけない保護者の話・ヤングケアラーの問題・ネットを通じた集まりへの心配
- 3班:BPファシリテーターの活動内容に関して・赤ちゃんを育てる保護者の孤立
- 4班:オンライン授業を受けるために仕事を休まないといけない保護者の話・マスク着用の子どもの心身に与える影響、人との関わりの減少の影響
- 5班:学童での学習支援で、担任の先生と連携を取るのが難しい。紙からICTでのやりとりに変更したが家庭によって連携が取りにくい
- 6班:保育所では換気・消毒等を徹底し、参観も短縮するなど、対応に追われている。運動量の減少の一方でゲームの時間が増えて目が悪くなっている。どうストレスを解消するか
参加者の感想・意見等
講演関係
- 子育て支援に役立つ内容だった。明日からの支援に活かしていきたい。
- 現在、計算の過程を書かない6年生のへの支援をしています。今日の研修を参考にさせていただきます。
- 放課後こども教室のこども支援に役立つ内容だった。
- 心理学のことが少し理解できたのが良かった。
- 子どもの課題に対しては、背後を見極め、やり方を変化させていくことが大切だと理解できた。
- 心理学を用いた子どもへの支援方法について学ぶことができた。子どもの気持ちを理解して上手な声かけをしていけるよう努力していきたい。
- ワーキングメモリーが年齢によって違っていることやどうかかわっていけばいいかなど、具体的で分かりやすかった。
- 学童保育の現場では、学習習慣をつける程度が精一杯で、学習面における支援まではできない。
- これまで自然にやってきたことも、言葉にして説明して貰うと、行動の輪郭が自信や確信に繋がると感じました。
グループワーク関係
- コロナ以降、リモートでの研修ばかりだったので、ディスカッションが新鮮でした。
- 様々なジャンルの人と話しができたのが良かった。
- オンラインでなく、直接に話しをしたり聞いたり出来ることのありがたさを感じた。
- ともに児童に関わる方たちの話を聞くことができ、大変参考になりました。
- グループワークでの意見交換はとても良かった。職種を超えた内容の話が勉強になった。
- 自分とは違った視点からの話を聞けたのが良かった。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課