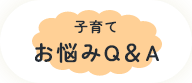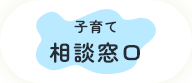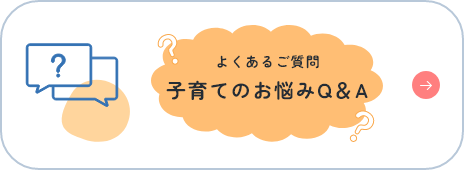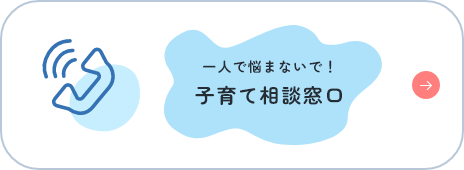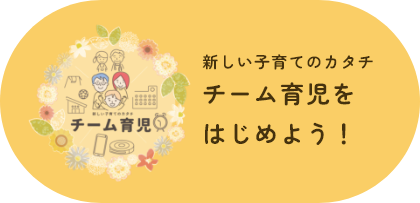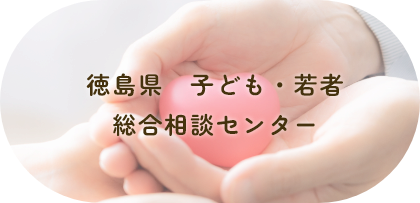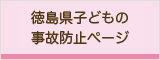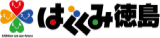令和3年度地域子育て支援ネットワーク研修会
日時
令和4年2月17日(木)14:00~16:00
場所
徳島市万代町3丁目5-3
徳島県職員会館 2階 第1・第2会議室
参加者数
14名
その他
本年度の本講座は、検温、換気、マスク着用、手指のアルコール消毒、会場内の消毒、講義形式での実施など新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じて開催。
「多様化する家庭の子育てと地域子育て支援の課題」
講師:岡山 千賀子さん(徳島文理大学人間生活学部児童学科准教授)



子育て支援者としての専門的な見識を深めるとともに、各子育て支援関係者が互いに必要な情報を共有し、子育てを地域全体で支え合う仕組みづくりを共に考える機会とすることを目的に「地域子育て支援ネットワーク研修会」を開催しました。今回は、徳島文理大学人間生活学部児童学科准教授の岡山千賀子さんを講師に迎え、多様化する家庭の子育てと地域子育て支援の課題ついて学びました。
講演
1 多様化する家庭
近年は、「一定しない家族」となっている。
以下のように、家族の姿が変容する。
家族は、一般的に男女が結婚してスタートし、その間に子どもが生まれて「核家族」となるが、共働きなどで子どもを育てられない。
- 祖父母に助けを求めて同居し「核家族」から「拡大家族」になる。
- 子どもが大きくなったら祖父母の助けが不要となり、再び「核家族」に戻る。
- 祖父母が年を取り介護が必要となり、また再び「拡大家族」となる。
少子化は、家庭・家族の変化や多様性に関わっている。
(1)結婚観
結婚観は変わる。
(2012厚生労働省白書)
Q1 約60年前と比べて結婚率(人口に対する値)は増えたか、減ったか?
A1 (半分以下に)減った。
60年前当時は、結婚しないとマズイとの思いがあった。今は、結婚するかどうかは個人の勝手という時代になっている。
Q2 生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合)?
A2 男性20% 女性10%
女性の方が結婚の圧迫感が強い?
Q2-2 なぜ結婚しないのか?
A2-2
- <独身の利点>
- (男女とも)1. 行動や生き方が自由
- (男性)2. 金銭的に裕福
- (女性)2. 広い友人関係を保ちやすい
- <結婚の利点>
- (男性)1. 精神的安らぎの場を得られる 2.子どもや家庭を持てる
- (女性)1. 子どもを持つことができる 2.精神的安らぎが得られる
Q3 「結婚は必ずするべきだ」と「結婚はした方が良い」という考え方の割合は?
(2010年内閣府調査)
(20~49歳の男女約1000人)
A3 日本65%(スウェーデン35%アメリカ53%韓国75%)
Q4 日本の現在の離婚率は?
A4 30%
離婚に抵抗感がなくなってきている⇒芸能人・アイドルの離婚報道も一因
個人の幸せのための離婚。
結婚は自由。社会的なことで結婚しなければいけないとか離婚してはいけないとか言われるものではなく、個人の自由の中で選択できるものであり自由度が高まってきている。
3組に1組が離婚という状況の中に子どもたちはいるという現実がある。皆さんの職場に、おそらく離婚家庭の子どもがいるはず。それを理解しその子の環境を知ることは、その子の発達を促すために非常に大事なこと。
(2)家族の形態(平成30年調査)
Q5 核家族の割合は?
A5 30%
1980年くらいをピークになだらかに下がっている。一方、ひとり親家庭が増加している。
Q6 ひとり親とその子どもの割合は?
A6 7%(少しずつ増加傾向)
前の婚姻で生まれた子どもを連れて再婚し、新しくできた家庭を「ステップファミリー」と言い、血縁関係のない親子で成立する。「ステップファミリー」は多くなってきて、会もあり相互に悩みや喜びを共有し合うということが全国的に広まっている。
いろんな家族の形態があり、これも多様化である。もちろん、ひとり親家庭の増加の背景には離婚がある。
2 多様化するLifeコース
- 「DINCS」Double Income No Kids 夫婦共働きで子どものいない家庭
- 「DEWKS」Double Employed With Kids 夫婦共働きで子どものいる家庭
■「ワークライフバランス」仕事も一生懸命するが、自分の生活も大事にする
24時間働いていた社会(家庭を顧みず仕事中心主義)から個人の生きがいを求める社会へ
⇒少子化対策の側面においても重要
3 働き方の多様化による子育て(内閣府2007)
世界と比較した日本の子育て(OECD2005調査)
Q7 3歳未満児の子を持つ母親の就業率は?
A7 30%
Q8 3~6歳未満児の子を持つ母親の就業率は?
A8 50%
母親は仕事をしながら子育てをしていて負担が大きい。
(ユニセフによるOECD諸国への2008年調査)
1人の指導員(保育士等)が3歳以上の子どもを何人でみているか?
1. オーストリア5人 2. スウェーデン6人 3. ニュージーランド7人・・・・・・・・・・・14. 日本15人以上(先進国25カ国中)
4 子どもと家庭を取り巻く状況
- 少子化世代が親になっていること
兄弟のいない夫婦が結婚し、子育ての仕方がよくわからない。 - 長時間労働と非正規雇用の増加
長い時間働いている割に給料が少ない。経済的に厳しい中で子育てをしている。 - 子どもの生活環境が変化していること
遊び場が少なくなった。 - 地域の共同関係が希薄化していること
近所の人を知らない。町内会・婦人会に入らない。コミュニティの繋がりが薄れている。 - ひとり親家庭や共働きの増加
5 子どもと家庭の課題
- 子育て支援ニーズの増大と多様化
保育士としてしなければいけないことがたくさんあるにもかかわらず、様々な家庭がありその状況に対応しなければならない。 - 仕事と家庭の両立が困難
特に、ひとり親家庭は仕事も子育ても一人でしなければならない。 - 家庭や地域の教育力低下
お爺ちゃんやお婆ちゃんから伝授されることがない状態で、乏しい知識の中で子どもを育てる大変さ。
家庭の中で子どもが上手く育つのが難しくなっている。だから、皆さん方のような地域の力が必要と国が強く言っている。家庭の教育力がなくなってきているから、地域や学校に頼るしかないというギリギリの状況。
しかし学校も厳しい、先生もヘトヘトの状態。地域社会だって指導員の待遇はなかなか良くならないし、人も足りない中で子どもをみなければいけない。
その上、地域コミュニティが弱くなって犯罪も増えてきているし、近所の人は声もかけてくれない。 - 子育ての不安やストレス
家庭で不安や育児ストレスが非常に高まってきている。それにより児童虐待が増加しているが、表に出ているのは氷山の一角であって実際はもっとあると言われている。
皆さん方も隠れた虐待を保育や放課後児童対策等の中で見つけなければならないという大変な状況になっている。 - 子どもの生活環境の変化に伴う影響
皆さん方のところに来ていない子どもの中には、良くない家庭環境で育っている子もいるという現実を知るべき。
6 地域の子育て支援者としてできること
(1) 子どもひとり一人の発達に応じた支援
- 取りこぼしが無い、持続可能な支援
取りこぼしの無いように、今を大切に、ずっと続くような支援を子どもたちにしていかなければならない。皆さん方は、子どもたちの財産を今、創っているわけだから。 - 子どもひとり一人を大切にする支援
大切なこの子どもの人生のために今、何をしなければならないか一生懸命に考えること。同時に、家庭が改善されないとどうにもならないので、上手く家庭を支援していくこと。根気強く、しかも上手な方法で。 - 次がない、今を大切にする支援
子育てにストップも後回しもない。子どもは成長しているのだから、今やらないと。
今が大事。この子には失敗したけど次の子は上手くやりますというわけにはいかない。
(2) 家庭支援
- ひとり親に対するアドバイスや相談
ひとり親家庭は場合によっては強い孤独感を持っているので、「お母さん、いつでも相談に乗るからね。話しに来てね」と柔らかく対応することが大事。 - 保護者の環境を把握した適切な助言や関わり
保護者の環境は各々違うし同じ家庭はないので、通り一辺倒ではなく、各家庭ごとに柔軟な対応が求められている。 - 子育てのプロとしての責任ある支援
(3) 子育て支援ネットワーク
- 支援者同士のネットワークづくりと充実
皆さん方はプロとはいえ、孤独である。一人では限界があるので、お互いがしっかりとネットワークをつくっていく、仲間をつくっていく。 - 産学官の共同支援に積極的に関わる
産学官の共同も大事。自分一人で全てを解決することは困難なので、いろんなところと連携をとっていく。働いている場所も内容も違うけど、仲間として共に頑張っていくことが必要。
感想
- とてもわかりやすい講演でした。明るく、楽しみながら子育て支援をしていくということを忘れずにいたいです。
- 多様化する家庭の中での夫婦の関係、子育ての環境も様々となっている中で、自分たちがその家庭に入り支援していくこともかなり難しくなっている。子どもたちも家庭の中でのしんどさを感じている現代。どう寄り添っていっていいのか考えさせられました。
- とてもわかりやすい伝え方で、お話を聞きながらも内観視できました。先生の子育ての話や仕事で経験してきたことを聞かせていただき、私が知らない現状を知ることができました。私は様々な分野を(少しだけですが)学んできましたので、どんな形で役に立てるのかを真剣に考えようと思いました。
- とても優しい気持ちになれる講義でした。ありがとうございました。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課