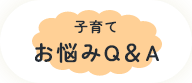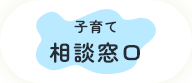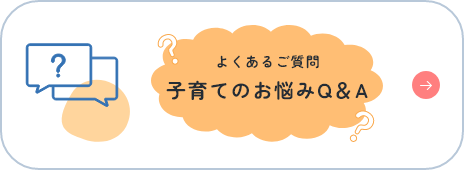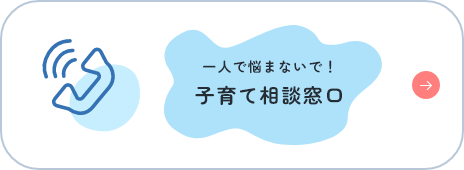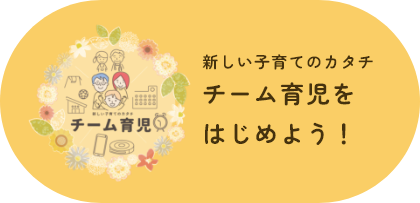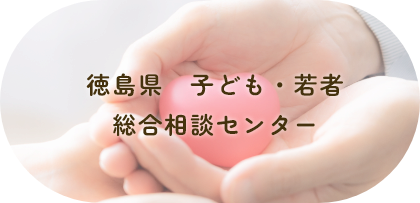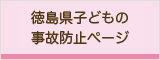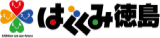令和6年度 第3回 被災児童保育ボランティア養成講座(報告)
- 日時:令和6年10月4日(金)13:00~16:00
- 参加者数:21名
- 場所:徳島市山城町東浜傍示1-1 ときわプラザ学習室(アスティとくしま2階)
講座「災害時、障がいのあるお子さんへの支援とは 」
講師:岡嶋 和代さん(社会福祉法人みらい 副部長 児童部門リーダー)
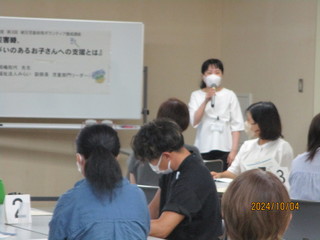

自己紹介
1.自分の名前と好きなものを書く。
2.グループ内で事前に書いた名前を呼び合い、ぬいぐるみ等でキャッチボールをする。例:うどんが好きな〇〇さんと呼び、〇〇さんにぬいぐるみを投げ、キャッチしてもらう。
◇◇◇講座の概要(流れ)◇◇◇
◎ 障がいについて(児童福祉法に沿った障がいの種類と説明)
⇩
- 身体障害…言語障害のある子どもには、負荷がかからないように言葉だけでなく、確認できる絵、カード、文字等で伝える。ルールの見える化
- 知的障害
- 難病
- 発達障害…身体障害と比べ、外見では分かりにくい。社会的コミュニケーションが取りにくく、言葉の理解や急な予定変更は苦手。見え方や聞こえ方にも特徴があり、漢字の捉え方も独特。(二重に見える、ゆがんで見える等)
◎ グループワーク1…言葉を使わずに絵や動作で相手に伝える。


◎ グループワーク2…両方意識する伝え方
- 継次処理…情報を順序よく処理していく。
- 同時処理…情報の関連性を把握し全体的に処理していく。
例:自分の荷物を持って(1.)広場に移動(2.)しましょう。
言葉だけではなく、伝わる方法を考える。
伝え方はいろいろで正解はない。
◎ 災害時や避難所では
発達障がい等の目に見えない障がいを抱えている子どもは、周りの人には、本人や家族の困り感を分かってもらうことが難しい。避難所での生活や災害時はいつもと異なる状況であるため、普段通りの生活が出来にくい。
対処の1つとして
⇩
- 分からないことの不安と恐怖を和らげる…何が起こっているか?の情報を与える。「誰と」・「どこで」・「何をするのか」「どうなったら終わりか」
- 落ち着ける環境の確保…個別環境の確保(平常時からテントやダンボールハウスに慣れておく。)
- 日頃から非常食に慣れ試食をしておく
- コーピンググッズ等準備しておく…ストレスを緩和し、触ることで集中でき、周りに目がいかず落ち着ける。
⇩


参加者の感想
- 言葉だけではなく、絵や行動での伝え方があることなど、特性や環境要因を考えて、相手を理解することが大切、今まで考えてなかったことを知れてとてもよかったです。岡嶋先生の講座をきっかけにもっと勉強していきたいと思いました。
- 岡嶋先生のお話を聞くのを楽しみにしていました。今日受講できて良かったです。
- 良い勉強になりました。
- コーピンググッズなど、実際に体感でき、分かりやすかったです。感覚や心的な部分、考えたことはあったけど、想像以上に大変な思いを抱え生活していること、まずは知れたことが、大変大きかったです。
- 前庭覚と固有覚について、詳しくお話を聞くことができてよかった。発災時に大人も落ちつかない中、特別な支援を要する子の「海の中で見えない部分」があるかも知れない。その子の行動の背景は?と立ち止まる、そして考える、このアクションがとれるかとれないかで、子どもが安心にすごせるかにかかわるな~と思った。
- グループワークで、いろいろ話し合うのが楽しかった。
- 施設に来ている子どものことを具体的に思いうかべながら受講しました。普段の行動の中にも、彼なりの捉え方や様々な要因(感覚や外的要因)が影響していたのかなと思いあたることがいくつかありました。多くのことを知れたので、配慮が今後自分にも出来そうだなと感じました。
- 特別支援学級で勤めた経験があり、個々の子どもに特徴があることは実感していた。講師の先生のいろんな事例で具体的にわかり易く話をしていただき、とてもよくわかった。子どもを落ちつかすため、周りのことに目が移らないような手だてとしていろんなグッズがあることを知り、今後の支援に参考になった。(特に被災地では大切かと)
- グループワークもよかったし、いろんな情報を知り、何かの役に立てるよう工夫していきたいです。
- 先生の話が聞きとりやすくわかりやすかったです。グループワークが時々あることで、話し合うこともでき、より理解が深まりました。
- 障がいのある子どもには、ルールを見える化すること、言葉でしっかり伝えるが伝わりにくい子には、絵、カードなどで伝える。ということがよくわかり今後は確実に伝わるよう、いろんな工夫をしていきたいと思います。伝わっているとの思いこみをしない。
- 自閉症の特性の例などをもう少し知りたかった。
- 障がいをもっている子どもたちには、いろいろなサポートが必要ということがまた、あらためてわかりました。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課