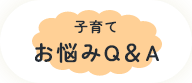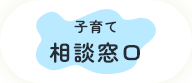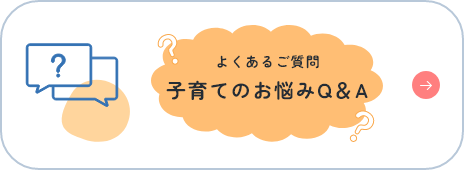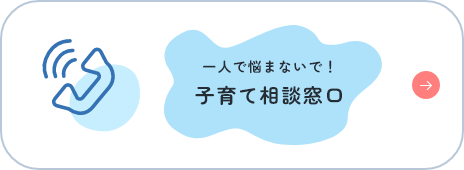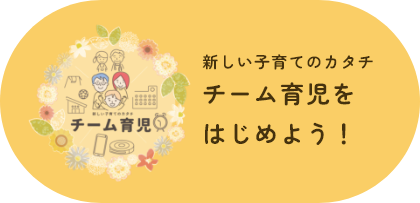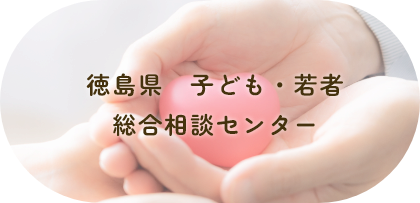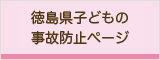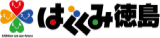令和6年度 第2回 被災児童保育ボランティア養成講座(報告)
- 日時:令和6年9月6日(金)13:00~16:00
- 参加者数:18名
- 場所:徳島市山城町東浜傍示1-1 ときわプラザ学習室(アスティとくしま2階)
講座「災害がもたらす心と身体の変化~困難に気付ける支援者であるために~ 」
講師:内海千種さん (徳島大学大学院社会産業理工学研究部 教授)


◇◇◇講座の概要(流れ)◇◇◇
1 ストレスについて
1. 日常のストレス
- 自分でどうにかできる➡(制御できる)
- どうなるか予測ができるか➡(ストレスの深刻度を下げる)
- これがいつまで続くのか➡(短時間で終われば我慢できる、終わりがある)
2. 予想できない災害では
- 自分では制御できない
- 自分ではどうしようもない
- 常に緊張感が続く
- いつまで続くかわからない
災害に遭うと安心・安全の概念が崩れる。ある出来事がストレッサー(ストレスの原因)となり、日常のストレスのように自分1人ではどうすることもできない。
2 体験学習(スクイグルゲーム)
1. 2人組になり1人が自由に線を描き、もう1人がその線に手を加え、何かの絵に仕上げる➡関係づくり ※子ども達との遊びの1つ


3 災害時特有の心身の反応
- 恐怖、不安、怒り、イライラ、悲しみ、抑鬱、否定的考え等
- 不眠、食欲不振、頭痛、持病の悪化、お酒と薬物、性的関係の問題等
- 罪悪感、羞恥心、無力感等
- フラッシュバック、覚醒亢進…(強いストレスを受け、周囲の状況に過敏になる)回避、解離
- 子どもでは、退行現象➡わがままになる、保護者がいないと泣き喚く等
- 遊びの変化➡災害に遭うということは、主体を奪われること
- 前兆(理由付け)➡自分のせいで出来事が起こった、自分が悪いことをしたからだと自分を責める(言うことを聞かなかった、宿題をしなかった等)
4 支援の際に覚えておきたいこと
- 支援の基本は、安心・安全の確保
- 自己効力感をもってもらうこと➡自分でできるという感覚
災害前の自分にできることをふり返ってもらう - わからないことを踏まえ沈黙を聞き寄り添う
- 主体は相手(被災者)
5 支援者のメンタルヘルス
- 自分自身のストレスを解消➡いろんな場面で使えるものをたくさんストックしておく 普段からストレス発散手段を考える
支援者自身が健康でなければいけない
参加者の感想
- 心やからだの反応において、わかりやすく教えてくださりとてもためになりました。安心・安全・自己効力感をキーワードに「あなたは?」「自分でやれること」「選択する」という主体を考えることができました。ご本人の人生を生きることについて考えるきっかけとなりました。支援は細く長く続けていくこと、そのために自分を大切にする、このことも重要ですね。
- 被災時に現状を目のあたりにした時、平常心でいられるか、心配になりました。
- 災害後の津波あそびなど、文献で知ってはいましたが、実際のお話を聞けて子ども達の心の変化など具体的に知れて良かったです。他にも有益な情報ばかりで、被災者の方のストレス、自分たちのストレスも知って、付き合い方、支援の仕方、覚えておきたいです。
- 子どものごっこ遊びは、言葉で伝えられない子達の表現の1つということがわかった。主体は子どもに置くことを忘れないようにします。
- 症状ではなく反応として促えるということがとても印象的でした。
地図
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課