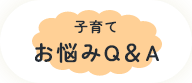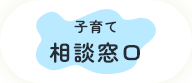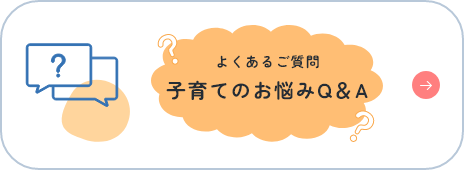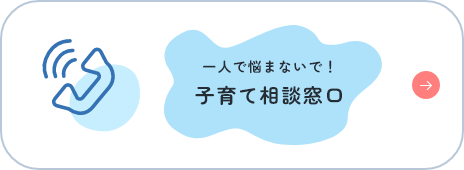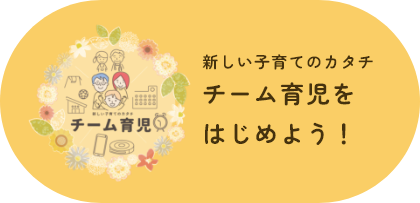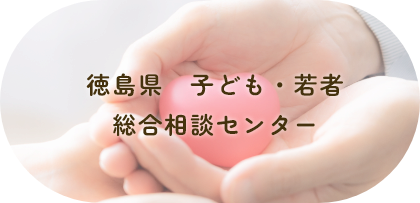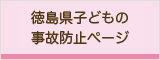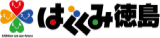仕事と家庭の両立に関する法律
妊娠・出産で退職した場合
1 再雇用特別措置等(育児介護休業法第27条)
事業主は、妊娠、出産、育児を理由として退職した者について、必要に応じ再雇用特別措置等を行うよう努めなければなりません。
「再雇用特別措置」とは、その退職の際に就業が可能になった時に退職前の事業主に再び雇用されることを希望する申し出をしていた者について、事業主が労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいいます。
妊娠中→産前産後休暇→育児休業→職場復帰→小学校入学まで
<妊娠中>
妊娠中の女性に対して、事業主は次のような配慮をすることが法律で定められています。
<産前産後休業>
- 産前産後の休業(労働基準法第65条)
- 産前休業…出産予定の女性は、本人が請求することにより出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業を取ることができます。
- 産後休業…産後については、本人から請求がなくても産後8週間は原則として仕事に就かせてはいけません。ただし、出産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
- 休業中の賃金
- 法律で特に定めてはありませんので、労働者と使用者との話し合いにより取り決めることとなります。なお、健康保険に加入していれば、出産育児一時金(35万円)や、産前産後休業中に賃金の支払がない場合、一日につき標準報酬日額の60%(出産手当金)が支給されます。
<育児休業>
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づき、労働者が1歳に満たない子を養育するために一定期間休業することです。出産後、労働者から申し出のあった場合、事業主はこれを拒むことはできません。休業中は、事業主の賃金支払義務はなくなります。しかし、労使の交渉により、賃金等の支給をすることは可能です。
- 労働者は、以下の事項について記載した休業申出書を原則として休業開始予定日の1カ月前までに事業主に提出することにより育児休業することができます。事業主は、要件を満たした労働者の申し出を拒むことはできません。
- ア 育児休業申出の年月日
- イ 育児休業申出をする労働者の氏名
- ウ 育児休業申出の子の氏名、生年月日、続柄
- エ 育児休業開始予定日、終了予定日
- オ 育児休業申出の子以外に1歳未満の子がいる場合は、その子の氏名、生年月日、続柄
- カ 育児休業申出の子が養子の場合は養子縁組の効力が生じた日
- 育児休業の回数は、特別の事情がない限り、一人の子につき1回であり、申し出ることができる休業は連続したひとまとまりの期間の休業でなければなりません。
- (特別な事情)
- ア 産前産後休暇または新たな育児休業の開始により、休業が終了した場合で、その産前産後休暇または新たな育児休業の対象となる子が死亡、他人の養子になったこと等により、労働者と同居しなくなったとき。
- イ 介護休業の開始により、育児休業が終了した場合でその介護休業の対象となる家族が死亡、離婚により労働者との親族関係が消滅したとき
なお、子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合は、子が1歳6ヶ月に達するまで休業可能です。
- 労働者に以下の事情がある場合は、1回に限り、育児休業予定日より前の日に変更することができます。(繰上希望日の1週間前までに申し出ることが必要です)
- ア 出産予定日前の出生
- イ 子の親である配偶者の死亡
- ウ 配偶者の負傷又は疾病による子の養育困難
- エ 配偶者と子の同居の解消
- 休業終了日の繰り下げ
- 労働者は理由を問わず、1回に限り、休業終了予定日を当初予定日より後の日に繰り下げて変更することができます。(繰下希望日の1カ月前までに申し出ることが必要です)
- 育児休業申出の撤回(育児介護休業法第8条)
- 育児休業開始予定日の前日までに書面により撤回することができます。ただし、撤回した場合は、配偶者の死亡など特別の事情がない限り、その子については再度育児休業の申し出をすることができません
- 不利益取扱いの禁止(育児介護休業法第10条
- 事業主は、育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由に、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
- 育児休業に関連してあらかじめ定めるべき事項(育児介護休業法第21条)
また、このような定めを育児休業の申し出を行った労働者の取扱いを書面により明示しなければならない。
<職場復帰>
のいずれかの措置を講じなければなりません。
<小学校入学まで>
のいずれかの措置を講じなければなりません。
日々雇い入れられる者は対象となりませんが、期間を定めて雇用される者は対象となります。
上記の育児時間(労働基準法第67条)とは別の措置でありそれぞれ実施する必要があります。適用を受けたこと等を理由として労働者に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりませんし、また労働者が希望する期間を超えてその意に反して適用されるものであってはならない。
事業主は3歳から小学校就学までの子どもを養育する労働者に対しても、育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるように努めなければなりません。(育児介護休業法第24条)
© 徳島県 こども未来部 子育て応援課