文字サイズ
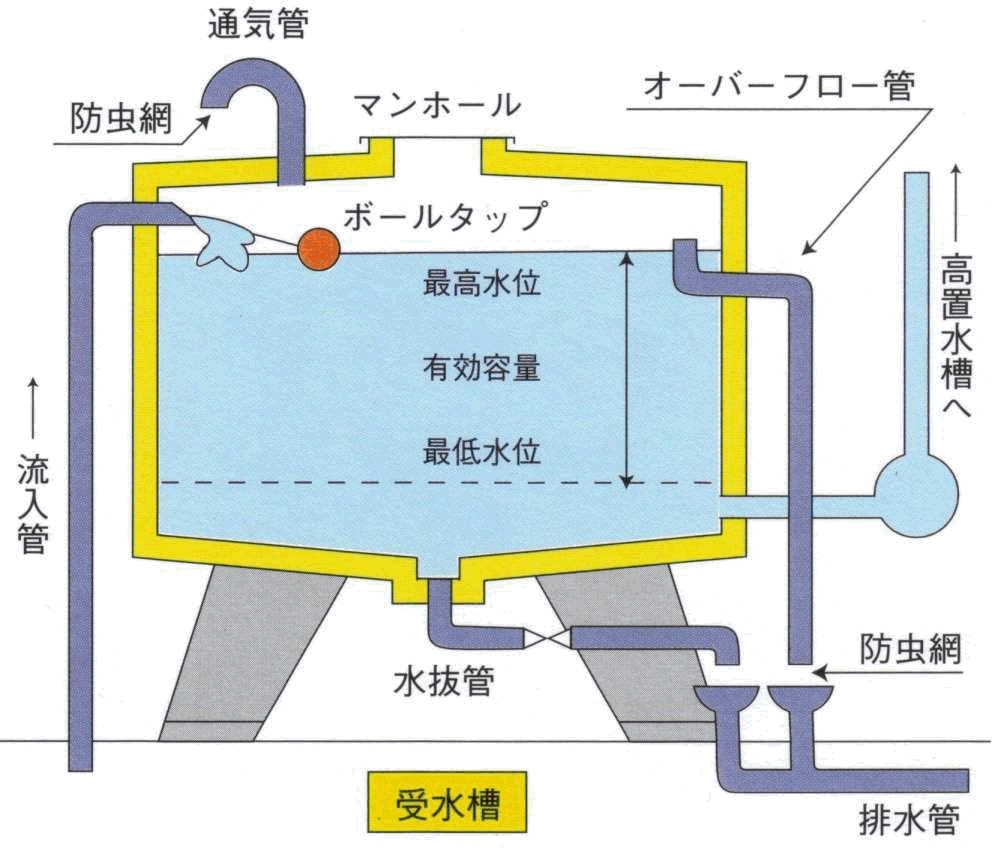
簡易専用水道の設置者は水道法に基づき、厚生省令等で定める管理基準に従って、その水道を管理しなければなりません。
| 事 項 | 回 数 | 摘 要 |
| 水槽の清掃 | 年1回 | 年1回定期的に行うこととし、管理者自ら行うか専門の清掃業者に依頼する。 |
| 水槽等の臨時点検 | 必要のつど | 地震、大雨など、水質に影響があると考えられるときに行う。 |
| 水質の外観検査 | 年1回以上 | 末端の給水栓において採水し、水の色、臭い、濁り等外観について検査する。(管理者は出来るだけ毎日水質のチェックを行ない、異常認めた場合は臨時の水質検査を実施するようにしてください。) |
| 水質検査 | 必要のつど | 水の外観検査に異常があったときは水質検査を実施する。 |
| 給水停止及び水質異常時の利用者への周知 | 必要のつど | 給水する水が人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水を停止し速やかに利用者へ周知する。 |
| 残留塩素の検査 | 必要のつど | 末端給水栓において検出されること。 |
これらの管理が適切に実施されるよう、設置者はその水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。徳島県では社団法人徳島県薬剤師会検査センターが登録を受けています。
例)施設の補修改善措置、水質異常に伴う水質検査結果、給水停止措置等の記録
小規模受水槽水道の衛生対策要領
(平成17年4月1日施行)
1目的
小規模受水槽水道を持つ施設の適正な管理、水質に関する適正な検査、汚濁汚染時における措置及び防止を定めることにより、衛生の確保を図ることを目的とする。
2実施主体
県が市町村の協力を得て連携を図りつつ実施する。
3対象施設
この要領において対象となる小規模受水槽水道は、受水槽の有効容量が10m3までのものとする。(ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受けるものは除く。)
4小規模受水槽水道の管理基準
1)水槽の掃除を1年以内毎に1回、定期に行うこと。
2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3)給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を1年以内毎に1回定期に行うことただし、後記5に規定する管理状況についての定期検査を行っている場合はこの限りではない。
4)供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
5小規模受水槽水道の定期の検査実施
設置者又は管理者は、1年以内毎に小規模受水槽水道の管理状況について簡易専用水道に準じて定期の検査を受けるよう努めること。
6定期検査要領と検査後の措置
定期検査の項目は、水道法に規定する簡易専用水道に準じて行うこと。また、検査者は定期検査を行ったときは、設置者に対し「小規模受水槽水道定期検査監査済証」を発行するとともに、不備な点があれば内容の説明のほか、特に衛生上問題がある場合には保健所にその旨報告するよう助言を行うこととし、報告を受けた保健所は、市町村と連携し改善の指示を行うこと。
7その他
保健所及び市町村は、管内の小規模受水槽水道の管理指導を円滑に行うため、簡易専用水道に準じ台帳を作成し保存すること。また、新たな小規模受水槽水道を市町村が確認すれば、保健所に報告すること。